大阪市が挑む「受動喫煙ゼロ」への道
2025年4月に開催される大阪・関西万博に向けて、大阪市では「受動喫煙のない街づくり」を掲げ、喫煙環境の整備に力を入れてきました。2025年1月27日からは、市内全域での路上喫煙を禁止する取り組みが始まりました。これは単なる万博対策にとどまらず、美観の維持、非喫煙者の健康保護、観光都市としての魅力向上など、複合的な目的をもった施策です。

会場内は全面禁煙 喫煙者の行動は制限されすぎの声も?
万博のメイン会場となる夢洲では、敷地内すべてが禁煙エリアに指定されています。喫煙を希望する来場者は、東ゲート付近に設けられた2か所の会場外喫煙所を利用しなければなりません。これにより、喫煙のためには一度会場を出て、吸い終わった後に再入場の手続きを踏む必要があります。
実際に訪れた来場者からは、「吸える場所があるのはありがたいが、遠すぎる」「何度も出入りするのは面倒」といった声も寄せられています。再入場の列が長くなれば、時間的な負担も無視できません。
喫煙者にも配慮した整備支援制度
こうした動きに対応するため、大阪市では「市指定喫煙所設置経費等補助制度」を新設。一定の条件を満たせば、民間事業者が新たに設置する喫煙所に対し、最大1,000万円の補助が受けられる仕組みが整えられました。混雑緩和と分煙の両立が期待して、市内には万博期間中までに約140か所の喫煙所設置を目指しました。
受動喫煙のリスクと、条例改正の意義
2024年3月、大阪市議会で「路上喫煙防止条例」の改正案が可決され、市内全域が路上喫煙禁止エリアとなりました。違反者には過料1,000円が科され、加熱式たばこも規制対象です。これは受動喫煙による健康被害への懸念が根底にあります。
副流煙(タバコの先から立ち上る煙)や呼出煙(喫煙者が吐き出す煙)は、周囲の人にとって極めて有害であり、特に子どもや高齢者に深刻な健康リスクをもたらすことが知られています。さらに、タバコの煙に含まれる有害物質は家具や衣類に残留し、火を消した後も「三次喫煙(サードハンド・スモーク)」という形で影響を及ぼす可能性があります。
公共空間での喫煙ルールを明確化することは、非喫煙者が安心して過ごせる社会の実現につながります。
国際都市・大阪としての課題と展望
一方で、課題も残されています。大阪市の喫煙率は全国政令市の中でも高く(17.7%)、万博会期中には約2,820万人の来場が見込まれています。既存の喫煙所だけでは対応が難しい可能性があり、混雑対策と併せて分煙の周知や案内の強化が求められます。
さらに、海外からの観光客への配慮も不可欠です。日本と異なり、欧米諸国の多くでは屋内での喫煙規制はあるものの、路上での喫煙は禁止されていません。文化や価値観の違いをふまえ、多言語対応のサインやマナー啓発など、インバウンド対応としての柔軟な情報提供が鍵となるでしょう。
「Health Smoke-Free」とは
単なる喫煙の禁止を意味する言葉ではありません。それは、すべての人が安心して心地よく過ごせる空間づくりを目指す、共存と尊重の理念を表す言葉です。喫煙者・非喫煙者の双方が、互いの立場や健康を思いやりながら過ごせる環境。そこにこそ、本当の意味での“共生”が生まれます。


未来に向けて
万博を契機に進む大阪市の喫煙対策は、ただの規制強化ではなく、「安心して過ごせるまち」「受動喫煙から誰もが守られる社会」を目指すための重要な一歩です。喫煙者・非喫煙者双方が納得できる環境整備をどう進めていくか、その試金石としても、2025年の万博が注目されています。
愛煙家が喫煙所を探すのに、こちらのアプリが便利です。

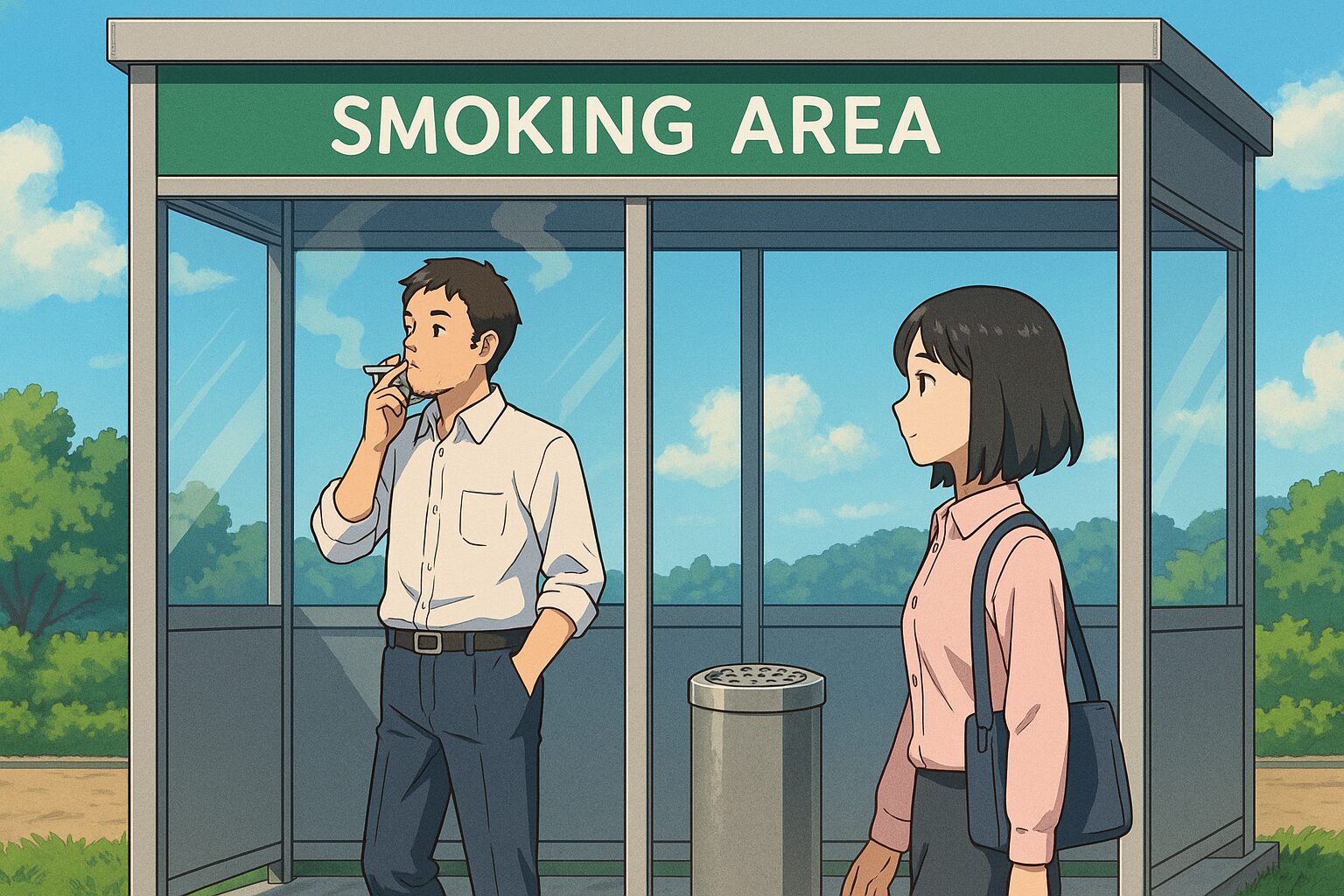





コメント